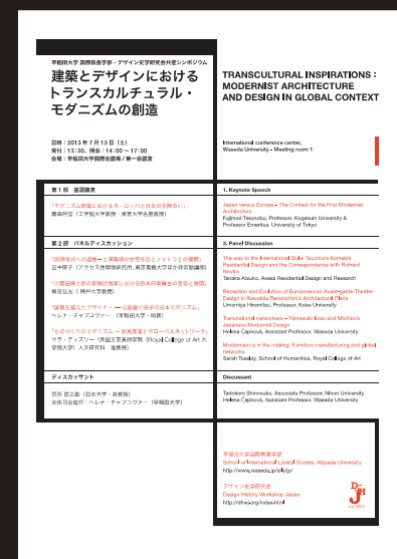東京国立近代美術館・工芸館「越境する日本人」展 関連事業 / デザイン史学研究会10周年記念シンポジウム
「オリエンタル・モダニティ:東アジアのデザイン史 1920-1990」
Oriental Modernity: East Asian Design History 1920-1990
第9回 シンポジウム「モホイ=ナジ再考─芸術の領域を越えて─」(京都国立近代美術館主催国際シンポジウムを後援します)
20世紀美術に「新しい視覚(ニュー・ヴィジョン)」をもたらしたハンガリー出身の芸術家、モホイ=ナジ・ラースロー(1895-1946)の全体像を紹介した日本で最初の展覧会「モホイ=ナジ / イン・モーション 視覚の実験室」の開催にあわせて国際シンポジウムを開催します。絵画、写真、彫刻、グラフィック・デザイン、映画、舞台美術、出版など多岐にわたるモホイ=ナジの活動は、20世紀美術が直面したさまざまな重要な課題を提示しています。本シンポジウムでは、モホイ=ナジの創作活動と思索の全容を解明するために、モホイ=ナジ研究の基礎を築いた専門家をはじめ、近現代美術史や写真、デザイン、映像などの研究者が集まり、それぞれの立場からモホイ=ナジ芸術の歴史的・今日的意義を検証します。
- 日 時:2011年7月23日(土)13:00~17:00
- 会 場:京都国立近代美術館1階講堂
- 参加費:聴講無料、当日開始時間の1時間前より受付にて整理券を配布します。通訳付き
* 会員のみなさまには、シンポジウム当日に限り、展覧会の招待券を配布しております。午前10時半~11時、エントランスに運営委員がお待ちしております。
- プログラム:
13:00~13:10 イントロダクション
○第1部:基調講演
13:10-13:40 「画家モホイ=ナジの誕生」
パシュート・クリスティナ(エドヴェシュ・ローランド大学名誉教授)
13:45-14:15 「モホイ=ナジと生命中心主義」
オリバー・ボーター(メニトバ大学准教授)
14:20-14:30 休憩
○第2部:報告+全体討議
14:30-14:50 「モホイ=ナジと中欧のアヴァンギャルド芸術」
井口壽乃(埼玉大学教授)
14:50-15:10 「モホイ=ナジと戦前の日本」
森下明彦(メディア・アーティスト)
15:10-16:10 全体討議
16:10-16:20 休憩
16:20-16:45 全体からの質疑応答
16:45-17:00 まとめ
第8回 シンポジウム「世界デザイン会議1960再考─WoDeCo 50周年をめぐって─」
1960年に世界デザイン会議(WoDeCo)が東京で開催されて今年で50年になります。テーマ「今世紀の全体像、デザイナーは人類の未来社会に何を寄与するか」を掲げ、国内外の建築家、デザイナー、評論家が一堂に会し、6日間に渡って議論されたこの会議は、その後日本のデザイン界に大きな影響を残しました。日本デザイン史の転換点にあたる1960年代、その契機となったWoDeCoを再び問い直すことをとおして、今日のデザインのありかたを検証します。第1部では実際の参加者のおひとりにお話をうかがい、第2部でデザイン評論家との対談をおこないます。
- 日 時:2010年7月17日(土)午後2時から4時
- 会 場:津田塾大学 AVセンター1階
〒187-8577 東京都小平市津田町2-1-1 [アクセス]
- 参加費:一般1,000円、学生500円、会員無料(事前申込不要)
- プログラム:
13:30 受付
14:00 開会あいさつ
14:05 第1部:基調講演
15:00 第2部:対 談
- 柏木 博(武蔵野美術大学教授・デザイン評論家)
- 井上雅人(武庫川女子大学講師)
- 総合司会:井口壽乃(埼玉大学教授・デザイン史学研究会会長)
17:00閉会
第7回 シンポジウム「写真×プロパガンダ×デザイン」
モダングラフィックデザインと写真は視覚的コミュニケーションの性格から両輪のごとく発展し、特にモダニズム期に前衛芸術家によって発見された新しい視覚表現は、国境を超えて国際的な規模で拡大し、大衆文化形成に深く関わってきました。しかしそこには、はからずも政治的な場面で活用された写真とデザインは、芸術家の意図から離れ「前衛」から「キッチュ」へと変容するというパラドックスもみられます。
今回のシンポジウムでは、ユーゴスラヴィアの写真史家ミランカ・トージッチ教授と日本近代写真史の専門家・金子隆一氏、ポーランド美術史の加須屋明子氏をお招きして、こうしたモダニズムと視覚文化の問題をを討論します。
- 2009年7月25日(土)午後2時から5時
- 埼玉県立近代美術館2階講堂
さいたま市浦和区常盤9-30-1 [アクセス]
- 参加費 一般1,000円、学生500円、事前予約不要
(研究会会員および埼玉大学生は無料)
- 共催 埼玉大学大学院文化科学研究科
- プログラム
13:30 受付
14:00 開会あいさつ
14:05 第1部:基調講演
- ミランカ・トージッチ(ベオグラード芸術大学教授)
「第二次世界大戦後のユーゴスラヴィアにおける写真とプロパガンダ」
- 金子隆一(東京都写真美術館専門調査員)
「アマチュア写真家と『報道写真』」
- 加須屋明子(京都市立芸術大学准教授)
「ポーランドの視覚文化にみるポリティックス」
16:00 第2部:パネルディスカッション
- パネリスト:ミランカ・トージッチ、金子隆一、加須屋明子
- コーディネーター:井口壽乃(埼玉大学教授/研究会代表)
17:00 閉会
第6回 シンポジウム「デザインとメディア」
近代社会において、メディアはめまぐるしく発展してきましたが、そうしたメディアと人間のあいだをまさに物理的に「媒介」してきたのは、デザイン活動です。
デザイン史学研究会はこれまで、ジェンダーやミュージアム、デザインの歴史性、社会性といったさまざまな角度から、広く社会とデザインを論じる場を設けてきました。本シンポジウムでは、「メディア」に焦点をあて、メディアとしてのデザイン、あるいはメディアのためのデザインの働きについて、20 世紀から今日までを射程にいれて考察します。
|
- プログラム
13:30 受 付
14:00 羽原肅郎 氏(デザイン評論家)
「タイポグラフィにおける可読性と品位について」
14:30 宮崎紀郎 氏(千葉大学グランドフェロー)
「メディアデザインがつくるもの─『ライフ』の写真をたどって」
15:00 原田 泰 氏(千葉工業大学准教授)
「ディスプレー表示を前提としたビジュアルデザインの手法」
15:30 森山朋絵 氏(東京都現代美術館学芸員・東京大学特任准教授)
「メディアアートの最前線」
16:00 パネルディスカッション
17:00 閉 会
|
第5回 シンポジウム「デザイン×テクスト×コンテクスト——誰のためのデザイン史?」
グローバルな視点からデザイン史研究の発展の経緯を見てみますと、20世紀初頭までは、主に工芸家やデザイナーなどの実践家によってその歴史が語り継がれ、両大戦間期にニコラウス・ぺヴスナーやハーバート・リードのようなモダニストのイデオローグたちによってデザイン史はモダン・デザインの発展史として登場するに至りました。その後、デザインにおける近代運動への批判の高まりとともに1970年代以降、その姿を大きく変えて今日まで継承されてきています。果たしてデザイン史研究は誰のためにあるのでしょうか。自文化や異文化理解のためデザイン史、企業家や消費者のためのデザイン史、デザイナーやクリエイターのためのデザイン史、鑑賞教育や体験学習のためのデザイン史——このシンポジウムでは、こうしたデザイン史研究の今日的射程を巡って語り合いたいと思います。
- 2007年7月16日(月・祝)午後1時から5時
- 埼玉大学 東京ステーション・カレッジ[アクセス]
- 参加費 一般1,500円、学生500円(研究会会員は無料)
- 共催 埼玉大学大学院文化科学研究科

[印刷用PDF] |
- プログラム
- 第1部 基調講演
- 第2部 基調報告
- 栄久庵祥二(日本大学教授)
- 長澤忠徳(デザイン・コンサルタント、武蔵野美術大学教授)
- 第3部 パネルディスカッション
- パネリスト:ジョン・へスケット、栄久庵祥二、長澤忠徳
- コーディネーター:井口壽乃(埼玉大学教授、デザイン史学研究会副代表)
|
第4回 シンポジウム「ジェンダーとモダン・デザイン——作り手としての女性/使い手としての女性」
これまでデザイン史の研究主題のひとつとして20世紀のモダニズムが盛んに論議されてきました。しかしそうした論議は、おうおうにして男性によって形成された視点からによるものでありました。そのような意味で、女性がどのようにモダニズムというイデオロギーに介在してきたのかという視座からの具体的な検証と歴史への再配置へ向けての学術的作業は、まさしく、近年ようやく注目されはじめた営みであるといえるでしょう。本シンポジウムでは、以上のような日本におけるこの領域の萌芽的状況をふまえながら、「ジェンダーとモダン・デザイン」を主要テーマとして取り上げ、とくに「作り手としての女性/使い手としての女性」の役割に焦点をあて、論議を深めたいと思います。
 |
- プログラム
- 第1部 基調講演
- 第2部 基調報告
- 常見美紀子(京都女子大学助教授)
- 神野由紀(関東学院大学助教授)
- 第3部 パネルディスカッション
- パネリスト:ペニー・スパーク、常見美紀子、神野由紀
- コーディネーター:菅靖子(津田塾大学助教授)
|
第3回 シンポジウム「日本におけるデザインのミュージアム——現状と未来」
デザインという行為をとおして視覚世界や物質文化は形成され、そのなかで現代に生きる私たちは日常の生活を営み、社会的文化的アイデンティティーをかたちづくってきました。そうしたデザインはこれまでどのような視点からコレクションされ、展示されてきたのでしょうか。このシンポジウムでは、現状の認識を深めるとともに、21世紀の日本におけるデザインのミュージアムについてさまざまな立場や観点から語り合いたいと思います。
 |
- プログラム
- 第1部 基調講演
- 木村一男(名古屋学芸大学メディア造形学部学部長、元JIDA会長)
- 第2部 基調報告
- 橋本啓子(インディペンデント・キュレーター、元東京都現代美術館学芸員)
- キム・サンキュー(韓国ハンガラム・デザインミュージアム学芸員)
- 第3部 パネルディスカッション
- パネリスト:木村一男、橋本啓子、キム・サンキュー
- コーディネーター:井口壽乃(埼玉大学助教授、デザイン史学研究会副代表)
|
第2回 シンポジウム「戦後復興期の日本デザイン」
戦後日本の経済復興は目覚しいものがあり、私たちの生活様式を大きく塗り替えることになりました。そうした発展を支えてきた力としてデザインを無視することはできません。戦後半世紀をへた今日、戦後復興期の日本デザインが歩いてきた道のりを、学術、教育、振興、実践のそれぞれの視点から検証したいと思います。
- 2004年7月3日(土)午後1時から5時30分
- 津田塾大学AVホール
 |
- プログラム
- 第1部 基調講演
- 回想のデザイン史研究/利光功(大分県立芸術文化短期大学学長)
- 戦後のデザイン教育をめぐって/日野永一(実践女子大学教授)
- デザイン振興行政に携わって/小関利紀也(高岡短期大学名誉教授)
- GKインダストリアルデザイン研究所とともに/曽根靖史(前近畿大学九州工学部教授)
- 第2部 パネルディスカッション
- パネリスト:利光功、日野永一、小関利紀也、曽根靖史
- コーディネーター:中山修一(神戸大学教授、デザイン史学研究会代表)
|
第1回 シンポジウム「21世紀におけるデザイン史研究」
私たちのデザイン史学研究会は、2002年11月22日に神戸大学で設立総会を開催し、正式に発足いたしました。この第1回のシンポジウムは2部で構成され、第1部では、デザイン史学研究会の設立を記念して、イギリスのブライトン大学のジョナサン・M・ウッダム教授をお招きし、「21世紀におけるデザイン史研究」と題して、デザイン史研究の過去を回顧するとともに、未来について展望していただきます。ウッダム教授は、1977年に英国に設立されたデザイン史学会のかつての会長で、現在はブライトン大学デザイン史研究センターの所長も務めています。続く第2部では、デザイン史学研究会の代表で神戸大学教授の中山修一とウッダム教授との対談を中心に、デザイン史学研究会の今後の活動について、参加者を含めて全員で討議したいと考えています。
 |
- プログラム
- 第1部 記念講演
- 回顧と展望——21世紀におけるデザイン史/ジョナサン・M・ウッダム(英国ブライトン大学教授)
- 第2部 パネルディスカッション
- パネリスト:ジョナサン・M・ウッダム(英国ブライトン大学教授)、中山修一(神戸大学教授、デザイン史学研究会代表)
- コーディネーター:井口壽乃(北九州市立大学助教授、デザイン史学研究会副代表)
|
Copyright © 2003-2007 Design History Workshop Japan. All rights reserved.